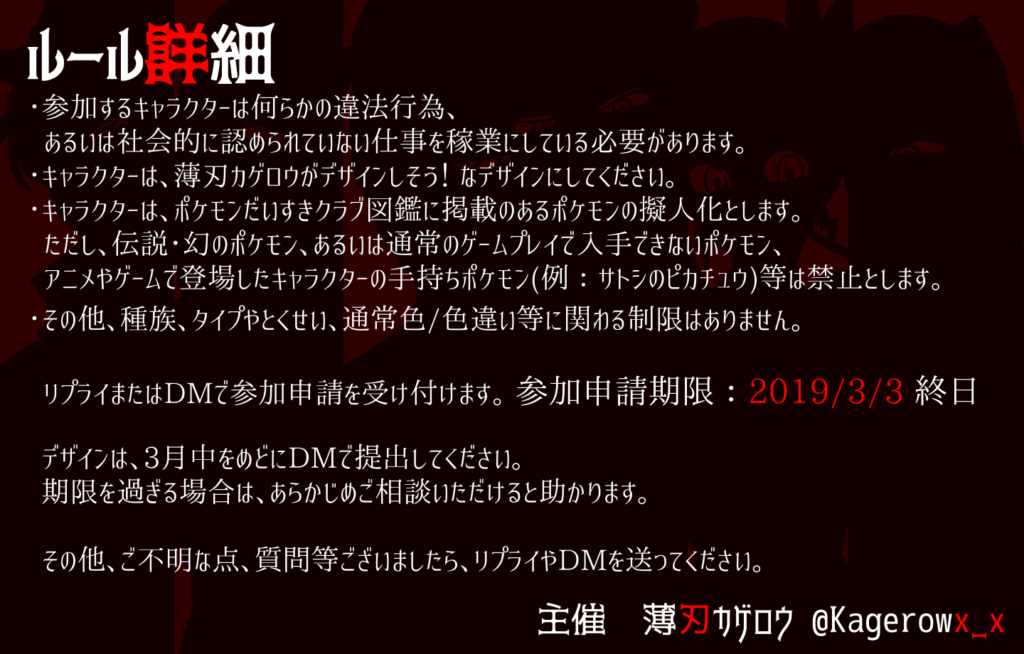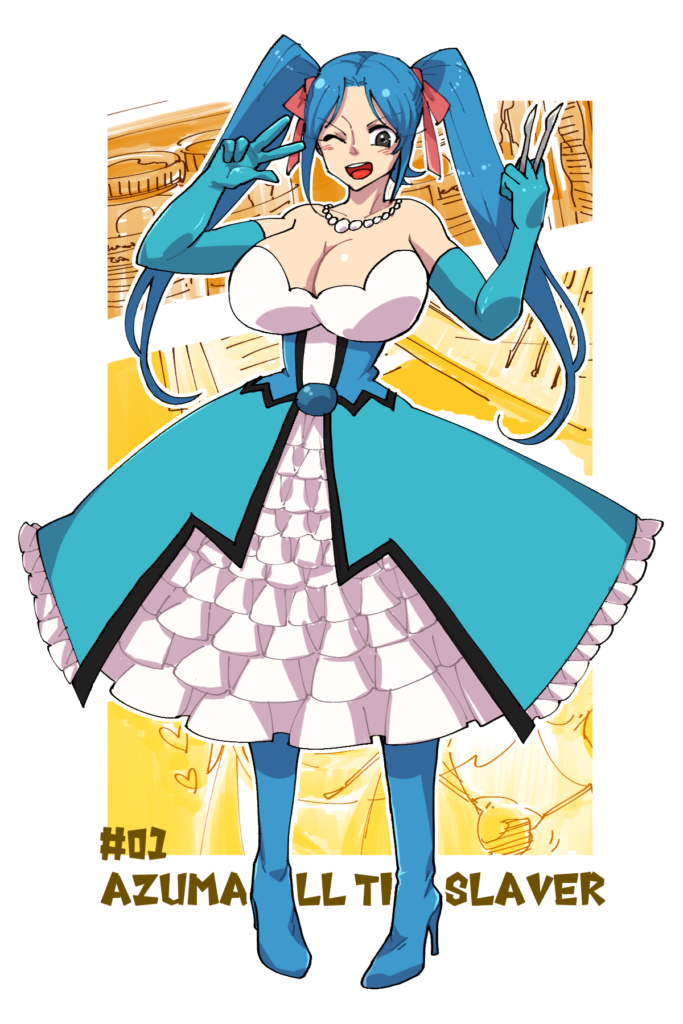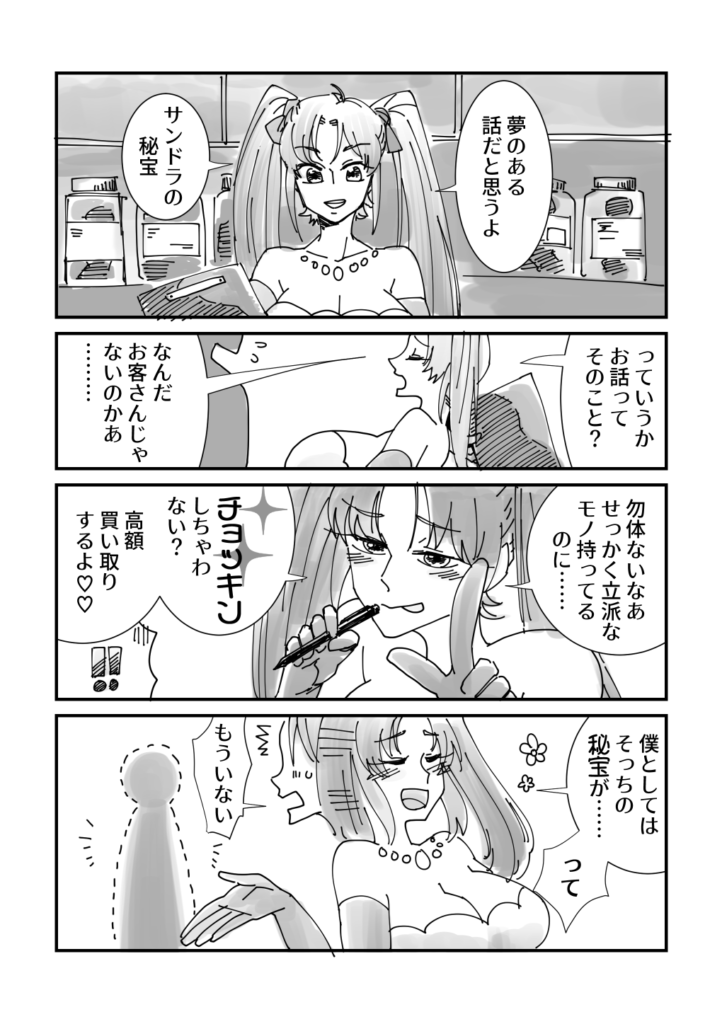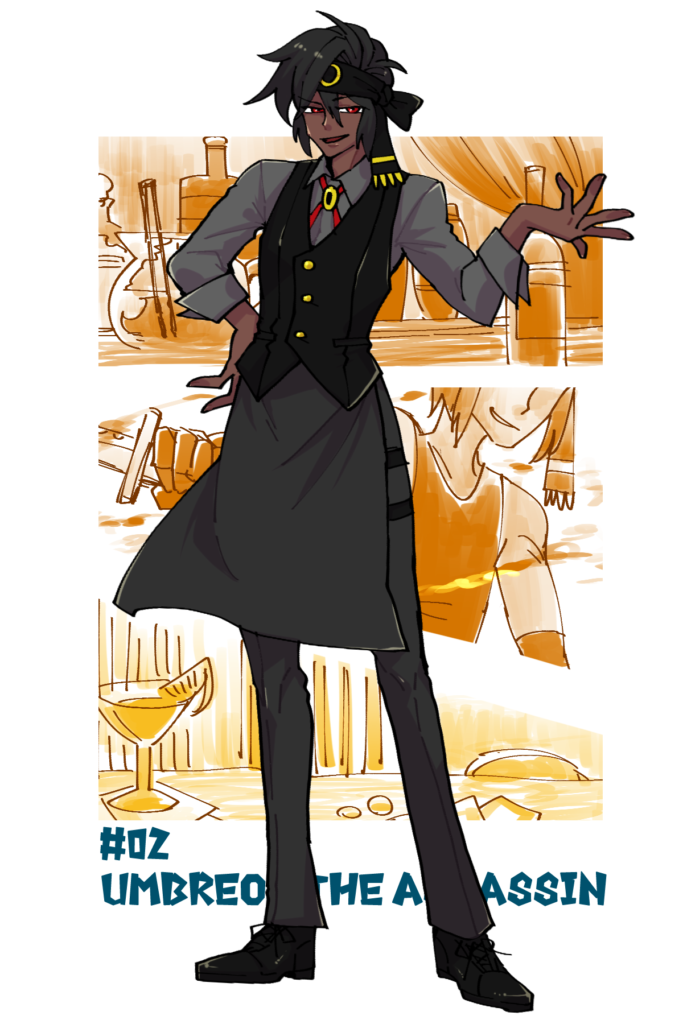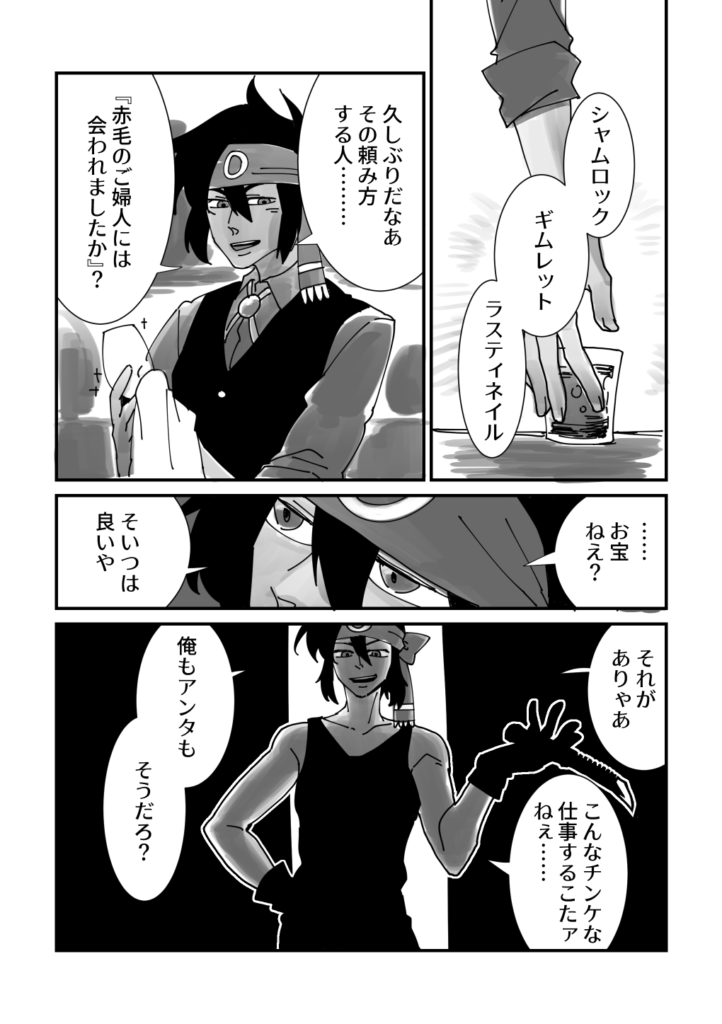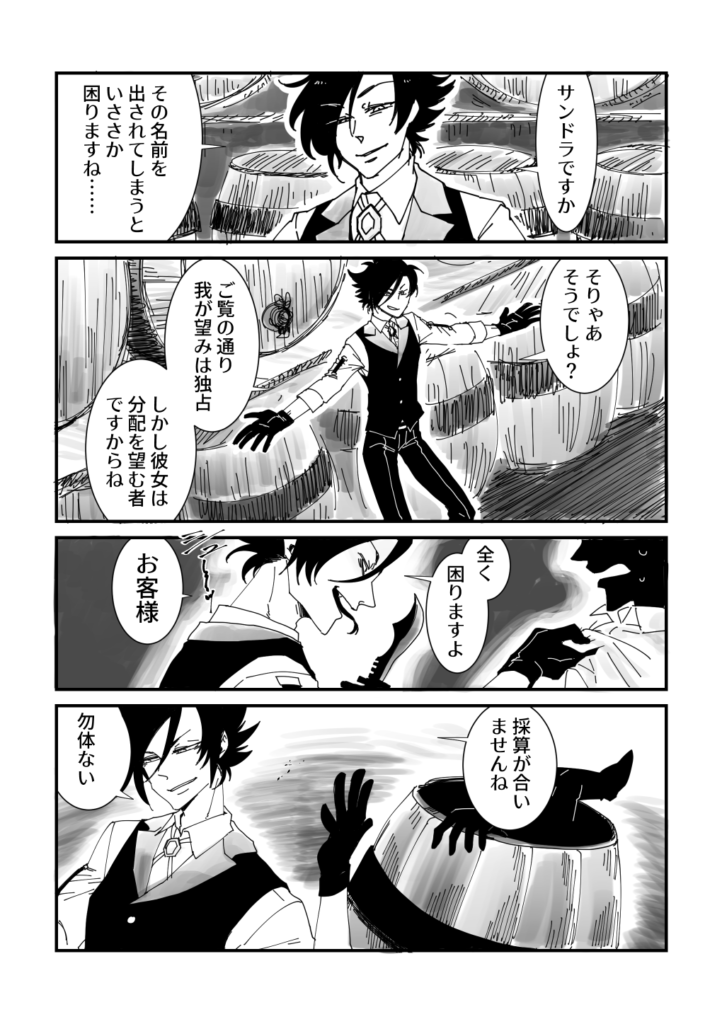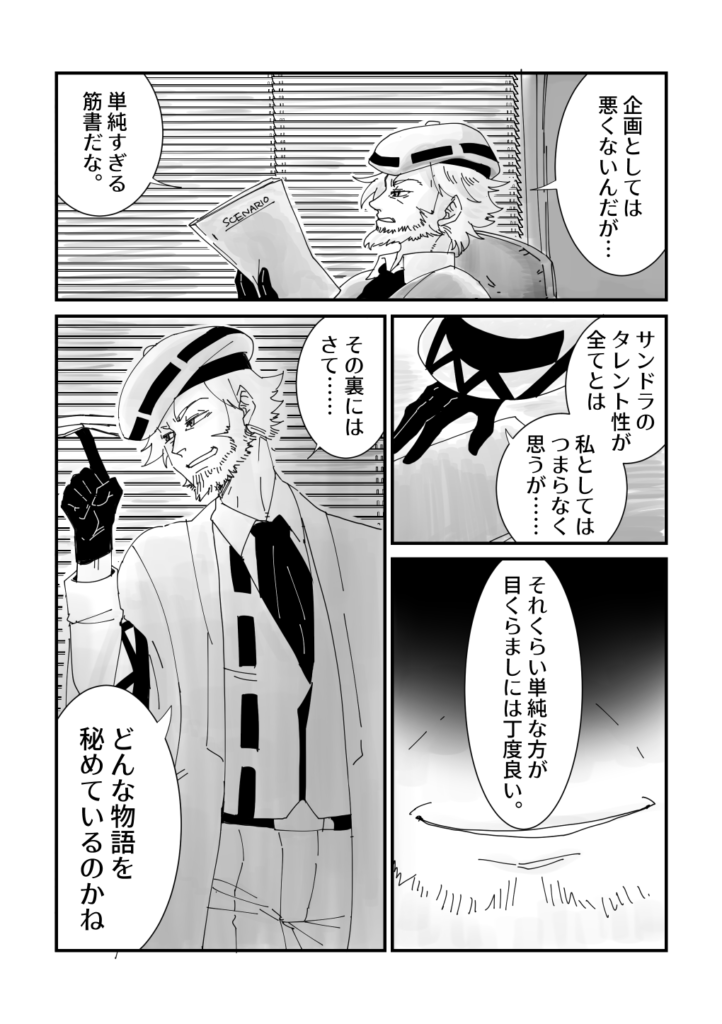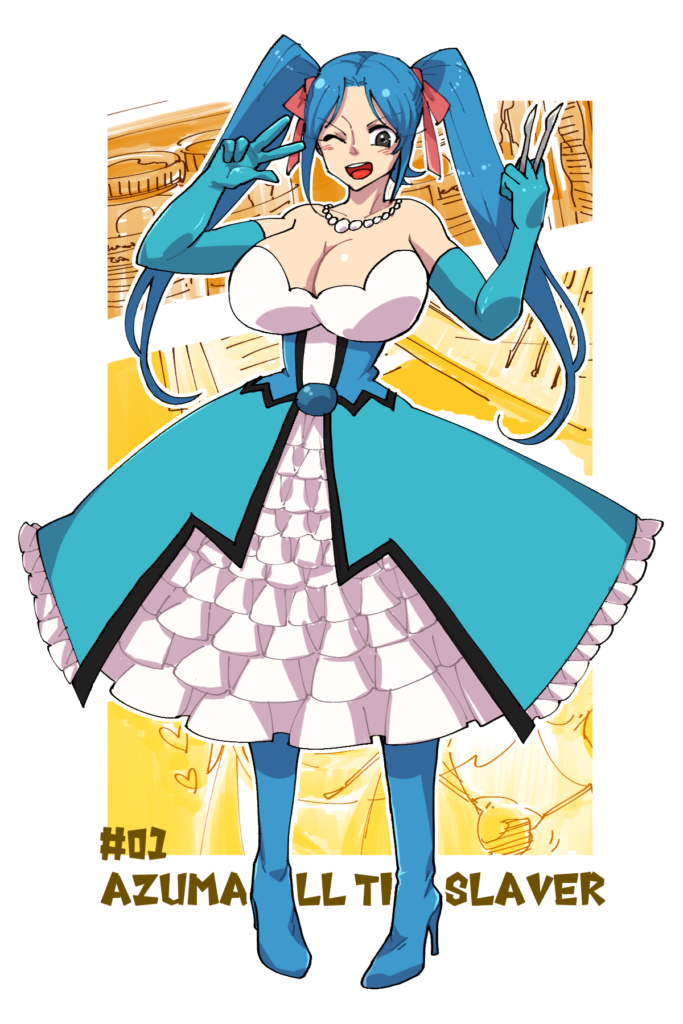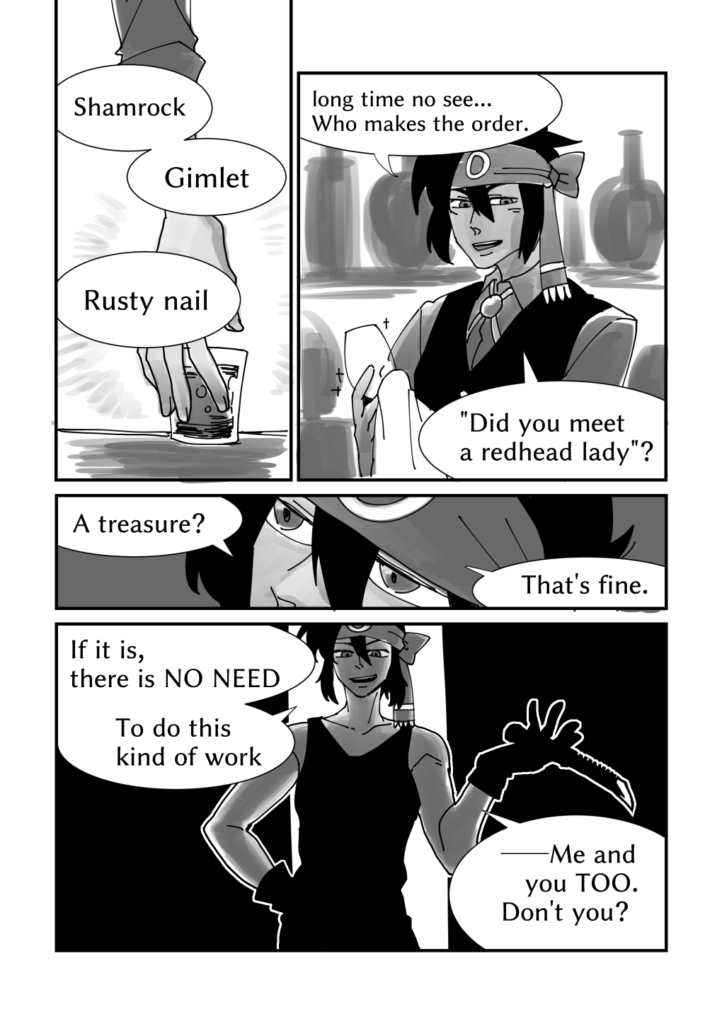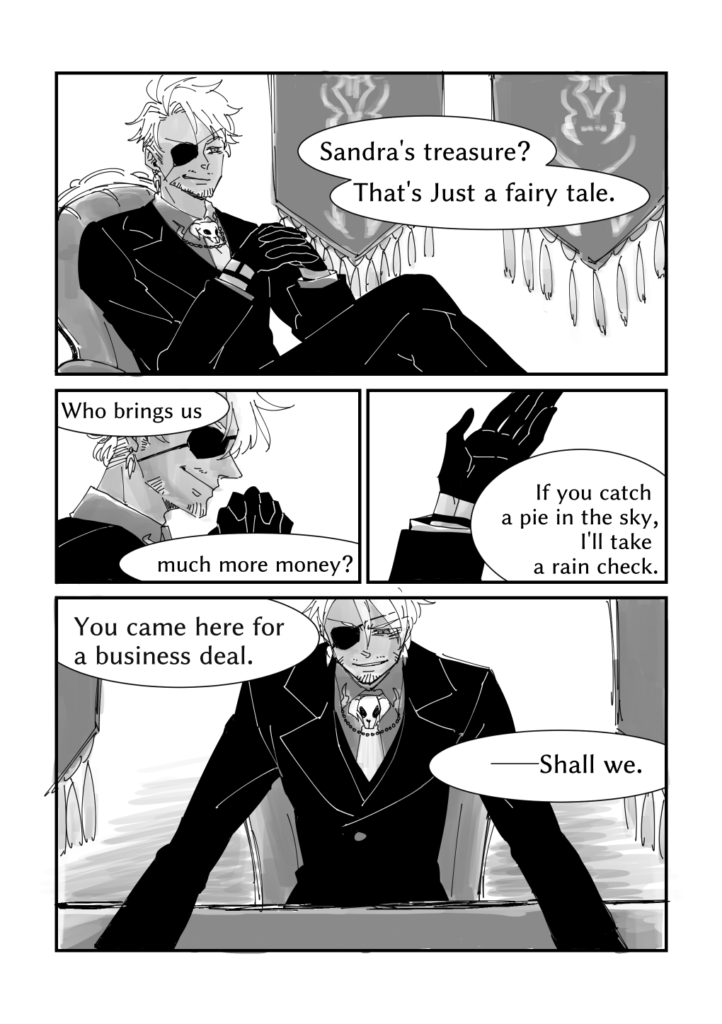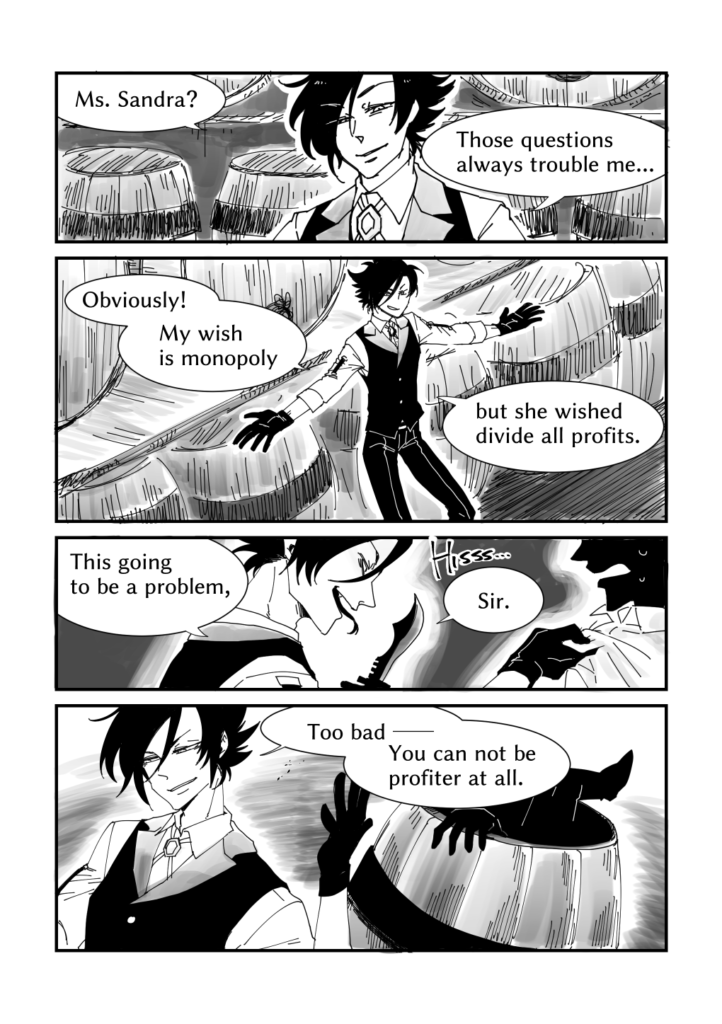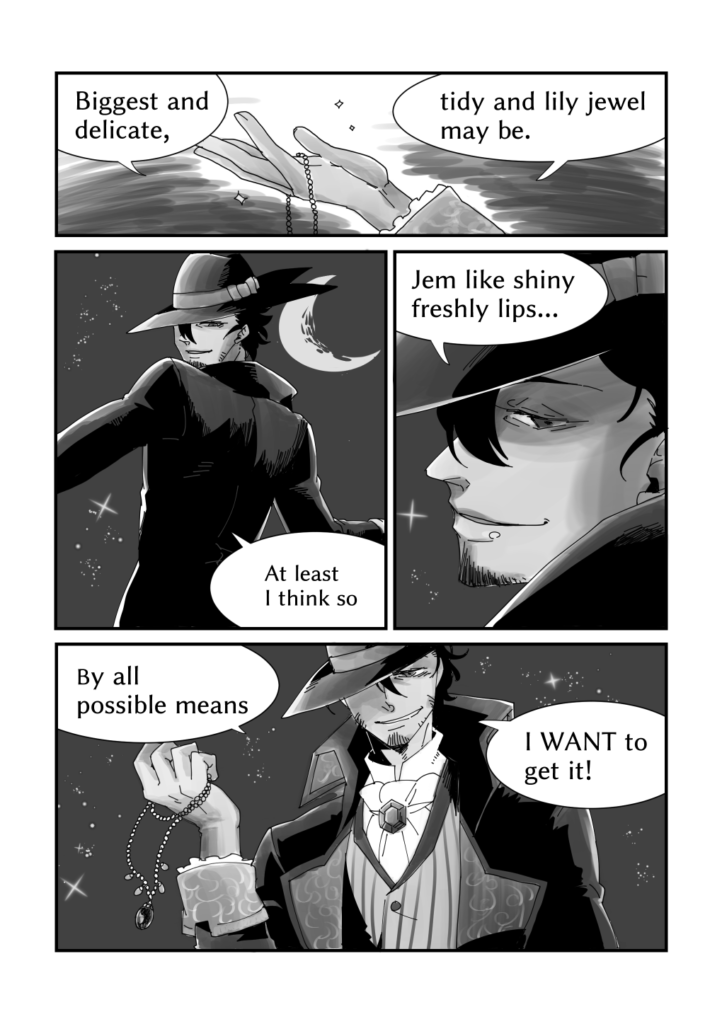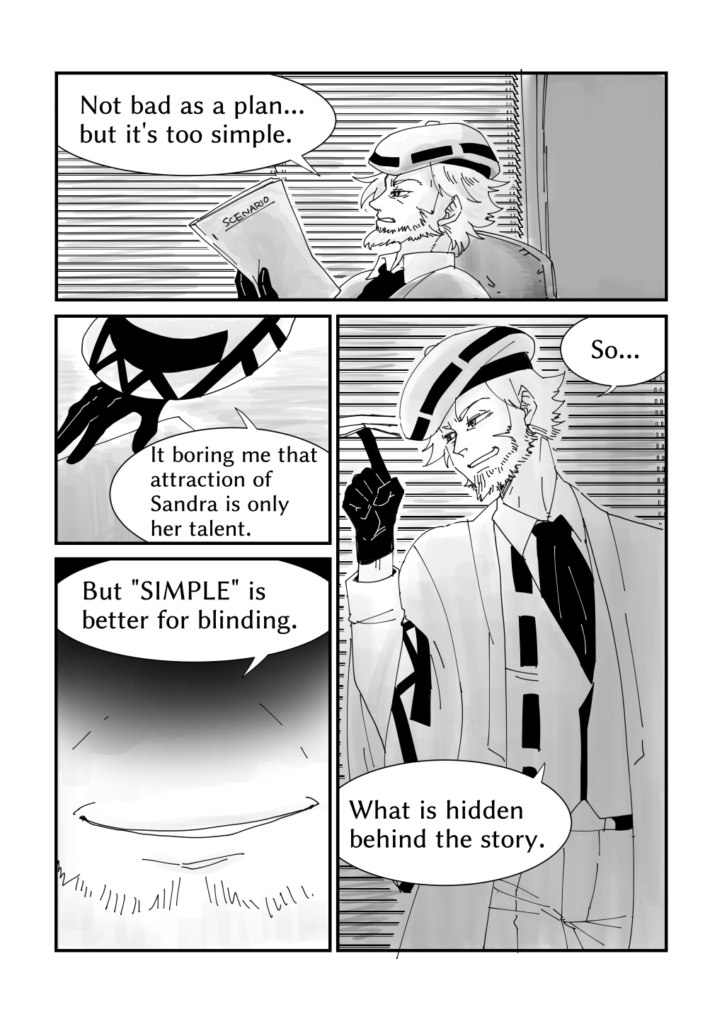※鞍オル/R18G
あ、と小さく呟いた。
不意に、背筋というか首筋というか、そのあたりがざわつくのを感じた。この感覚は言葉では説明しづらいものがある。
死後だか予後だか、この不思議な世界に暮らしていると、時折『こういうこと』があるのだ。前触れなどがあるわけではない。『イベント』としか言いようのない出来事。その上で、この感覚は——その。
流し見ていた映画を止めて、ちら、と鞍馬のほうを見た。かち合った視線は、既にじわじわと、欲の熱に焦げつき始めている。ああ……やる気なんだ、鞍馬。
下腹が熱くなる。俺も、これから起こることに期待してる。気づけば、媚びるように唇を歪めて微笑んでいた。
例えばの話。
相手をどれだけ傷つけても、死なないとして。
傷つけられる感覚が、至上の快楽に置き換えられていたとして。
流れ溢れる血肉が、天上の花蜜のように甘やかな美味であったとして。
その交わりが、貪りが、何にも代え難い欲求と愛情を持つのだとして……それを拒める者がどれだけ居るか。それは、日々互いに向ける単純な肉欲と、どれほどの違いがある?
やわらかなベッドに沈むように横たわり、天井を見上げて息を吐く。早く欲しい。早く、めちゃくちゃにしてほしい。抑えられない欲求が、ゆるゆると股座で形を持ちつつある。愛し気にそれを撫でられると、自然と甘えた声が喉から漏れた。
「ぅ、あ……♡」
「もう、こんなにして……。可愛いなァ、お前さんときたら……。」
こしょこしょ、下着越しに弄ばれ、息が荒くなる。ああもう意地悪しないで……。そう囁くと鞍馬は楽しそうに微笑んで、俺に被さってくる。脳が蕩けてしまいそうなほど何度も、緩く唇を重ねて、いよいよ我慢できなくなった俺は、鞍馬の舌先を少し噛んだ。
じわ、と広がるのは、血の味ではなくて。
それは鞍馬の味だ、としか言いようがないのだけど。どことなく高級なステーキ肉のような、香ばしくて食欲の唆る、それでいてひどく甘くて心地よい食味。きっとそれは、俺が思い描く『この世でいちばんおいしいもの』の味なんじゃないだろうか。
たっぷり絡め合った舌を離して、鞍馬は俺を見下ろしたまま、いっそう楽し気に、悪戯っぽく笑っていた。
「欲しがりめ。——そんなに俺に殺されたいか、オル。」
そうだよ。
そうだよ、俺は鞍馬に殺されたいんだ。
きっと今、俺は誰にも見せられないような、ひどく歪んだ顔で笑っているんだろうな。
シャツを捲られた胸元に、一瞬、冷たく固いものを押し当てられる。息を呑む間にその質感は、すう、と肌の内へと滑り込んだ。
「んッ……!♡」
刃の感触に遅れて、電流のような痛みがじわじわと広がる。吐息が震える。小太刀を当てられた肌はパンケーキのようにふわりと切れ、ぱんぱんに詰まった、どろりとした血糊のソースを溢れさせる。それが肌から滴り落ちる前に、鞍馬の舌に掬われる。
「ん、ぁ゙っ♡♡」
「甘い。お前さんは本当に、どこも甘いなァ……」
唇を俺の血で赤くしたまま、鞍馬はにんまり笑う。獣のようにぎらついた金の瞳が細められ、獲物に狙いを定めるように、俺の肌を見回している。傷口を愛撫するようにくりくりとなぞられ、その度に腰が跳ねてしまう。
「あ゙♡ ッぅ゙♡ ぃじわるッ……もっと……ぉ゙♡」
「くく。今日はやけにせっかちだな、お前さん……?」
開けられた傷口を、両手でぐっと広げる。皮膚が、腹膜がみしみしと裂けるのが分かる。痛い。痛い。甘えた悲鳴が咽喉を抜けていく。
「ぁ゙、っ♡ ね……ほら゙っ……食べて……?♡♡ 俺のこと、ぜんぶっ……めちゃくちゃに、してね゙っ……?♡♡ 」
ごくり、と唾を飲み込む音が聞こえた気がする。勢い歯を立てられ、貪られる。
呼吸する間さえ惜しむように、柔らかい肉を、溢れ出す血潮を、齧り取り飲み込む。あまりに乱暴で貪欲で、見境のない食事の様を見せつけられて、思わず嬉しくなってしまう。
「あぁ゙っ♡ あぅ゙ぅっ♡ 鞍馬♡ くらま゙ぁ、美味しい゙っ?♡♡ おいし……?♡♡」
はしたなく血糊に濡れている頬に手を伸ばす。その掌に齧り付かれ、不意の痛覚に頭が焼けてしまいそうになる。べろりと傷を舐め上げられ、心底嬉しそうな声で、美味い、と囁かれる。
俺には俺の身体がどんな味をしているのか分からない。俺が舐めても、俺の血は生臭い鉄の味しかしない。そういうものらしい。
でも、普段甘いものなんかそうそう好まない鞍馬が、甘くて美味い、と砂糖菓子のように俺を褒めてくれる。大好物のように貪ってくれる。それがたまらなく嬉しく、それだけで達してしまいそうなほどだ。
この状況がどんな魔術やまやかしだったとしても、鞍馬がそれを望み、欲しいと願ってくれるなら、それで構わない。
「オル、……オル。こっちも良いか?」
ぐっ、と猛ったものを押し付けられる。俺なんかもう、触られもしないのに何回もイっちゃってるのに。それでも下着の上からも分かるぐらいガチガチに勃起してるの、知ってるくせに。そんなふうに、悪戯を思いついた子みたいな顔で。
拒む理由なんかない。むしろ、こんな有様の自分でも鞍馬は愛してくれるのだと安心する。俺は狡い男だ。だから、せめていちばん可愛い声でねだる。
「ちょうだい、鞍馬……♡」
「ひぃっ♡ ぎ、……ッく♡♡ イぐッ、も、イッてるぅ゙っ♡♡ ぃ、にゃぁ゙っ♡♡♡ にゃぁぁぅ゙ぅぅッ♡♡♡」
何度も深く貫かれる快感と、その度にぼろぼろに食い破られた部分が痺れるように痛む。どこが気持ちいいのか、どこを絶頂に導かれているのか分からない。ぐりぐりといちばん良いところを擦られて、息が詰まり、獣の唸りのような嬌声と共に漏らすように射精する。それも何度目なのかわからない。
「は、は……ッ、また漏らしてるぞ、オル……♡ そんなに好いか? もっと良くしてやろうか、ほら……!」
ぐじゅ、と湿った音と共に、腑に手を突っ込まれる。外から……中からか? どっちでもいいや。ぎゅっと内臓を圧迫され、電流のような痛みが脊髄を駆け上がる。
「に゙ゃっ!?♡♡♡ やぁ゙っ♡♡ だめだめだめっ♡♡♡ それほんどにだめだから゙っッ!!♡♡」
「あぁ゙……♡ ほら、そんな締めるなッ……♡」
ぐっ、ぐっ、と何度も腑を押される。神経が焼き切れそうなほどの痛みの中、確実に溜まっていく、甘い痺れのような期待。それが溢れてしまったら、どうなってしまうのだろう。少し怖い。
「や゙、らめ、っ♡ こわいっ…鞍馬ぁ゙、イくのこわい゙ぃ♡♡ イぐのだめっっ♡♡ すごいの゙きちゃうぅ゙ッッ♡♡」
どれだけ訴えても、鞍馬は止まってくれない。助けを求めるように手を伸ばし、汗ばんだ首筋に縋りつく。気づけば視界は涙で滲んでいた。
「怖いか? 怖いな? ふふ、オル、めちゃくちゃにして欲しかったんだもんな?♡ お前さんがそう言ったんだぞ……!♡♡」
「ひぃ゙♡♡ やら゙イぐ♡♡ イ゙ぃっ………ッッッ!♡♡♡」
「っ俺も……ッ、く、……!♡♡」
熱い精液を注がれるのを腹の奥で感じながら、目の前が真っ白になる。ちかちかと、頭の中で火花が散っている気がする。浮遊感に一拍置いて、やっとそれが絶頂の快楽であると理解する。息がうまく吸えず、がくがくと身体が震える。
「————っ、あ゛ぁぁぁぁぁぁぁ゙ぁぁぁぁ………!♡♡♡♡」
性器を抜かれ、投げ出された身体からは、ずるりと内臓が溢れていった。力の抜けた太腿に、じわじわ、暖かいものが伝っていく。血と、もう随分とさらさらになってしまった精液とない混ぜになって、滴りはぐっしょりとシーツを濡らした。何回やらかしても、この瞬間はちょっとだけ恥ずかしい。
そんな俺の痴態まで、今は興奮材料になってしまっているのか。鞍馬はしなだれた腑を摘み上げると、やわく牙を立てた。ああ……そんなところまで、愛してくれなくたっていいのに。ゆるやかな痛みの中、鞍馬と目が合う。血濡れたその手が伸ばされ、頬に触れた。やっぱり自分の血は……生臭い。
「オル。俺のオルティ……。」
優しく、頬を撫でられる。その、天の色を写した黒と金の眼は、時折そんなふうに、寂しそうな表情を見せる。
俺のせいだ、と思う。
鞍馬に黙って消えてしまった俺のせい。何も言えなかった俺の。鞍馬に嘘を吐いた俺のせい。苦しんで、ひとりで死んだ俺のせいなんだ。そうせざるを得なかったとしても、その結果、鞍馬を苦しめたことはやっぱり……俺のせいなんだ。
鞍馬は、赦してくれている。改めて俺を迎え入れて、愛して、もう放しはしないと、俺と契ってくれた。それでも、あの時素直に伝えていれば、という気持ちはどうしたって湧いてくる。身体の苦痛がどれだけ置き換えられて、まやかしの快感に塗り替えられていても。この心の痛みだけは、痛みのままでそこにある。
鞍馬だってきっと、そうなのだろう。だから、俺のことを時々、どうしようもなく寂しい目で見るんだ。俺が本当にもう二度と、鞍馬を孤独にしないことを確かめたいから。
ああ、鞍馬、ごめん、俺はずっと知らなかった。鞍馬がそんなふうに、俺を想っていてくれたこと。ずっとずっと愛していたのに、俺は鞍馬を何も知らなかった。
それが俺のいちばんの罪だ。
『これ』は、もしかしたら、そんな不器用な俺たちに与えられた、浄罪の儀式のようなものなのかもしれない。殺したいほどの独占欲と、殺されたいほどの独占欲。それをそっと、心と身体に馴染ませるための優しい儀式。
「いいよ……良いよ、鞍馬。鞍馬に、ぜんぶあげる……。俺はぜんぶ、心も体も魂もぜんぶ、鞍馬のものだ……。」
「オル……、」
「愛してるよ、鞍馬、誰よりもいちばんに愛してる。もう、俺は何処にも行かない。ここに居る。」
だから最後まで、やって。
唇を重ねて、深く長く、息をするのも忘れるぐらい互いに舌を絡め合う。なんだか唾液まで甘やかな気がして、いつまでもこうしていたいと思った。名残惜しそうに音を立てて唇を離される。それから鞍馬のすらりと長い指が、俺の頬骨を、瞼をゆるく撫でた。ああ…、と鞍馬は、深く溜息を漏らした。
つ、と指先を滑らせて……ゆっくりと眼窩に差し込まれる。感じたことのない苦痛に暴れる身体は、いつの間にかがっちりと、鞍馬に組み伏せられていた。薄い飴細工でも割るみたいに、ぱきぱきと音を立てて頬骨が割れる。
「あ゛……っぅ゙…————!!!♡♡♡」
神経の束を引き千切られながら、がくがくと腰が震えて止まらなかった。お腹の奥が暖かくて、ずっと満たされているような心地だった。それと裏腹に喉の奥は血の味がして、思わず咳き込む。……そういえば、目と鼻と喉って奥で繋がってるんだっけか。
鞍馬は抜き取った俺の左の眼を、まるで飴玉でもそうするみたいに口に含むと、そのまま噛み砕いてしまった。もしかすると本当に、鞍馬にはそういう味と食感がするのかもしれない。空になった眼窩に唇を落として、ひび割れた骨ごと啜られ、齧られる。その音がじゃりじゃり、ざりざりと頭に直接響いてきて、その間中俺は情けなく喘いでは絶頂していた。鞍馬が顔を上げても、それで痛いのが止むわけではないから、俺はいつまでも馬鹿みたいに身体を跳ねさせて泣きじゃくり、シーツを握りしめたまま激痛に耐えていた。
「っだめ、ら゙め♡♡ イ゙くのとま゙んないっ♡♡ も゙、や゙だぁッ♡♡ きも゙ちいの、や゙ぁ♡♡ ひ、にゃぁ゙ぁぁぁ………!!!♡♡」
鞍馬が耳元で、何事か囁いてくれた気がする。きっと愛の言葉だっただろう。俺にはもう聞こえていなかったけど、頬に添えられた手は優しくて暖かかった気がするから。
目の裏の骨のところをとん、と叩かれる鈍い痛みの後、——俺は気を失った。
次に目を開けた時、俺は鞍馬の膝の上に乗せられて、緩く頭を撫でられていた。ソファの上で眠ってしまっていたのだろうか。
「オル。起きたか。」
まるで全部が夢だったかのようだ。
どこも何事もない。左眼を擦ると、涙がわずかに指先に沁みた。奇妙な、それでいて心地の良い泥濘の悪夢を見たみたいに、体の奥には気だるい満足感がある。
「鞍馬……、あ、映画……。」
画面には、流れていくエンドロールが映っていた。とてつもなく低予算なサメが出てきたところまでは覚えているのだが。
「よく分からん話だったが、お前さん……こういうの好きだったか……?」
「うん……。馬鹿馬鹿しくて好きなんだよ。頑張ってる感というかさ……。一生懸命な感じ? でも、いちばんは、こういうのを見てられる時間ができたのが嬉しいのかも。」
「そうか。」
ソファに座り直し、鞍馬にぴったりと寄り添う。肩口に頭を乗せて、掌を鞍馬の手と重ね合わせると、ぎゅっと力強く握られる。
「……嘘じゃないからね。俺はもう、何処にも行かないよ。鞍馬の側に居る……。」
そう囁くと、鞍馬は返事の代わりに唇を奪っていった。絡めた舌を少しだけ噛まれて……それは赦しだろうと、やっぱり俺は思った。