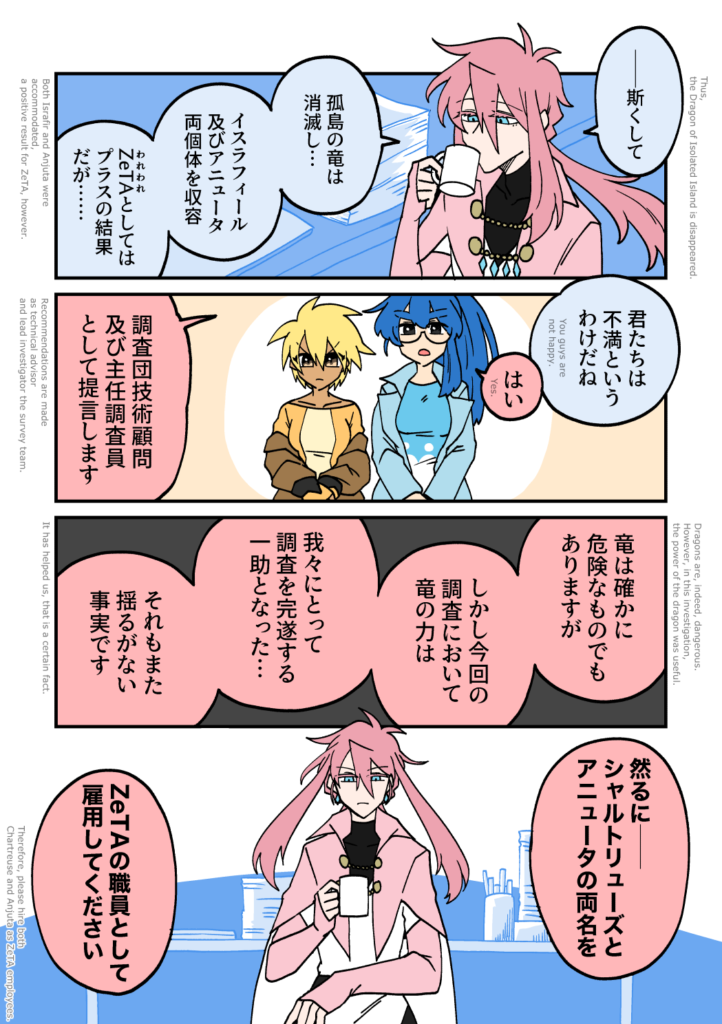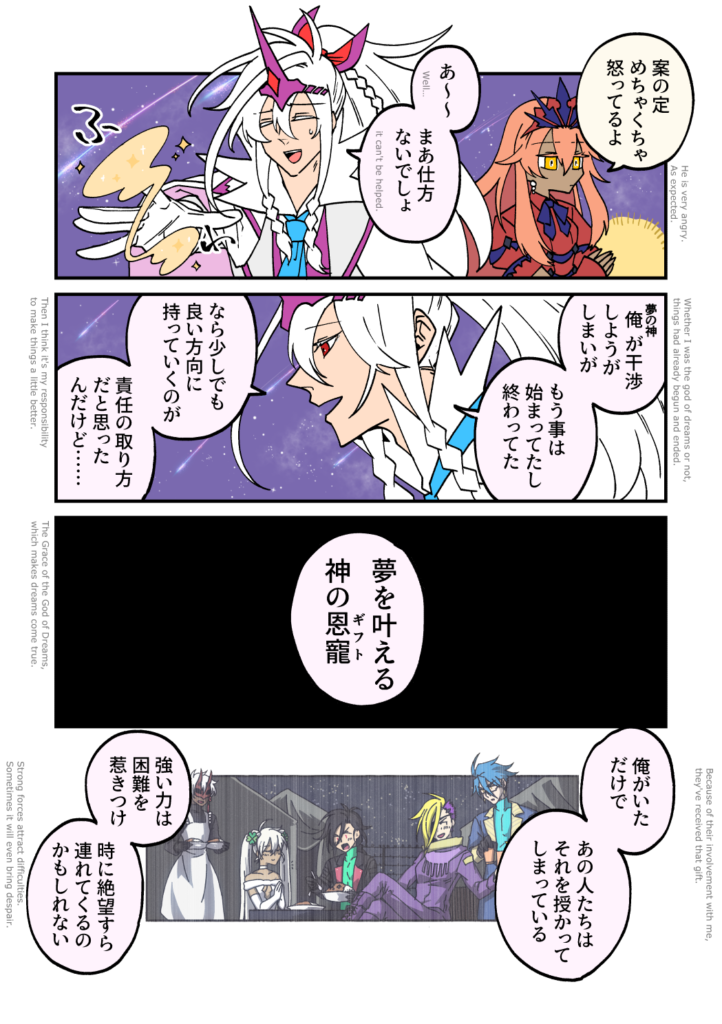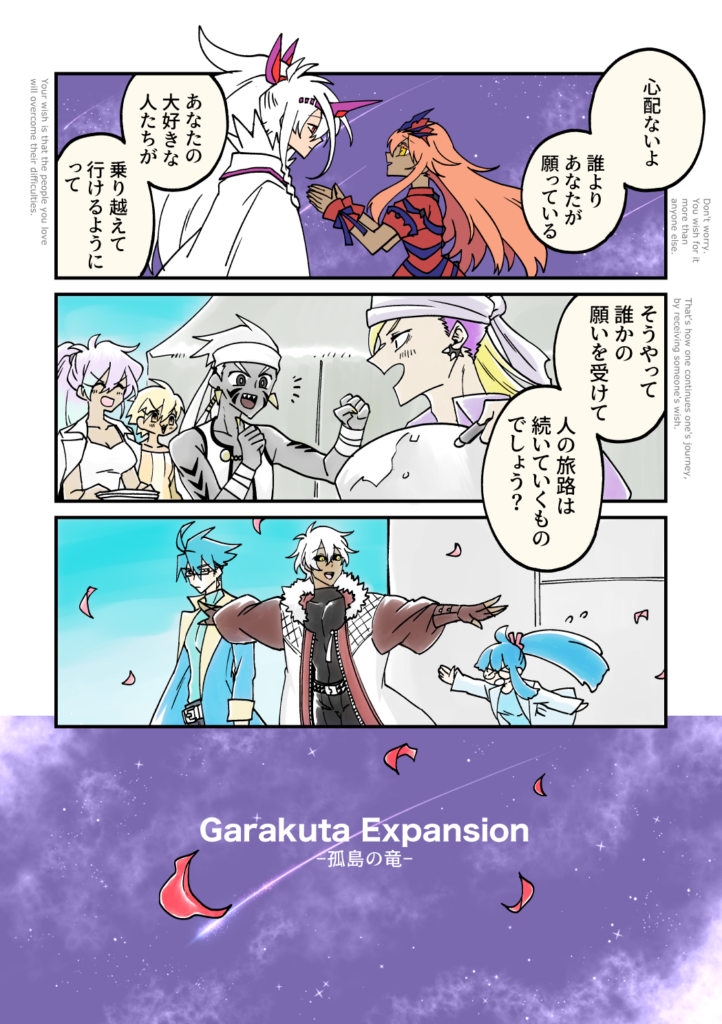カテゴリー: がらくた英雄伝説
オラクル・アドベント
瓦礫の中、ひとり月を見上げる少女がいる。
——それは正確にはヒトではなく、ヒトを模した容れ物である。
神造精霊Type-O、通称”オラクル”。ふたつに結った長い白髪、ドレスのような艶やかで繊細な衣装。ヒトであることを諦めた者たちのため、悪夢の神が織り上げた神秘。かの神の天使徒である少女たちは、みな似通った容姿をしている。優しき悪夢の神は、彼の手が掬い上げた者たちをそのように加工し、自らの端末として使用しているのだという。
ここにいるオラクルもまた、その端末のひとつである。小麦色の肌と碧い瞳、四ツ葉の髪飾りの”オラクル”、しかし彼女にはある特別な事情があった。
『彼女』は月を見上げ、思考している。オラクル、という名で呼ばれるようになり、どれほどの時が過ぎたのだろう。取り留めのない記憶を辿り、やがて彼女は深々と溜息をつき……足元で転がった、盗賊たちの遺体を見下ろした。
この端末の少女に宿っているのは、この世界とは枝を異にする世界から送られた魂だ。名を、オルティ・クラヴィアドという『彼』は、いまだにこの愛らしい少女の姿に慣れることができていない。ましてや、自分が送り込まれた理由になど、どうして馴染むことができるだろう。
悪夢の神は云う。共に世界を救おう、と、”オルティ”に手を差し伸べる。オルティは、手を取らざるを得なかった。オルティは死病の床にある。病床で滅び逝く、使い物にならない身体でも、まだお前の愛しいもののために出来ることがあるのだと、悪夢の神は甘く囁いた。もう二度と手に入らないものだとしても、その夢の断片だけを抱いて眠っていたオルティには、とても断れない勧誘だった。
そうしていざ訪れた世界で、少女の肉体を与えられた。その世界で生きる人を見た。死にゆく人を見た。全く、世界が変わろうが時代が変わろうが、竜という異形に蹂躙されていようが。人というものはどこまで行ってもヒトであった。やれ盗賊に襲われただの、出かけた少女が消えただの、騙されただの裏切られただの、なんの、かんの。なにもかも。オルティが嫌悪してやまない、『人』という悪性は、何処にでも存在したのだ。
——世界は、人類とは、本当に救われるに足るものなのか?
思考をやめ、オラクルは頭を振った。
それでも私はやらなければならない。せめて、私の愛したものだけでも守るために。彼らの救いになれると、そう信じていなければいられない。今にも絶望の荒波に叩き落とされそうな、綱渡りの際の際。オラクルはぎゅっと目を瞑る。せめて盗賊たちの弔いになるよう、信じてもいない女神に祈りを捧げる言葉を、小さな声で唱えた。
翌朝になって、オラクルは東へ進路を取り、廃墟の街を歩いていくことにした。
明け方わずかに雨が降り、地面はまだ濡れている。ハイヒールは泥水を跳ね上げた。”オルティ”ならば、それを不快に思っただろう。だが、今のオラクルは何を感じることもない。感情の全ては、オラクルの中に閉じ込められたままだ。
オラクルは、ラザロ・キャンプを目指していた。
彼女の意思ではない。彼女を管理している機関、ZeTAの指令によるものだった。耳元で微かに電子音がする。装着した小型インカムが起動していた。通信相手は、オルティをサポート……という名目で監視している職員だ。
「オラクル、早いっスねぇ。もう起きてたっスか」
アンセム。彼女はいつもこんな調子だ。きっと、彼女にはオラクルの正体も何も知らされてはいないのだろう。
オラクルは答えない。アンセムは、オラクルの反応がないことに構わず、一方的に会話を続ける。
「こっちは今起きたところっスよぉ。まだ眠いっス……。なんかここんとこ寝つき悪いんスよねー。あ、でも昨日は久しぶりにぐっすり眠れたんスよ! やっぱシャワーの使える日は違うっていうか、スッキリできるっスよね! ……って、聞いてます?」
「アンセム。定時報告の通信では?」
オラクルはようやく口を開いた。その声は冷たく、突き放すような響きを持っている。だが、その程度のことで怯むアンセムではなかった。彼女は気楽な口調で言う。
「ああ、そうなんスよ! 定時報告お願いするっス!」
「……定時報告。特に報告なし。問題なし。予定通り、正午ごろにキャンプへの到着予定。通信を切ります」
それだけ言うと、オラクルは通信を切断した。通信が切れる刹那、アンセムの静止が聞こえた気がしたが、無視した。
しばらく歩き続けていると、やがて前方に白煙が上がっているのが見えた。目的地、ラザロ・キャンプであろう。白煙ののろしを上げているのは、市場が開かれている証であると、オラクルはあらかじめアンセムから聞き及んでいた。オラクルは歩く速度を早めた。
◆
ラザロ・キャンプは、この荒廃した世界の中で最大の規模を誇る市場を兼ねている。かつて荒野であった場所には襤褸いテントが立ち並び、人々が行き交う。
ここでは誰もが自由に商売をし、そして物々交換によって必要なものを手に入れている。中にはZeTAの禁じた品を扱う者もいるらしいが、気に留める者はなかった。ラザロのキャンプではキャンプマスターであるラザロが法だ。そして、誰も彼もが生きるために必死だった。
オラクルは、そのにぎわいを眺めながら、キャンプの中心地を目指した。此度の訪問は、キャンプの主人であるラザロとの対面のためだ。彼は、この辺り一帯の物資流通の元締めである。
ZeTAはラザロと結んでいる。物資の提供であったり、情報の共有であったり、時には竜の討伐などの依頼を仲介したりと、様々な形で関わっていた。オラクルの仕事は、彼にZeTAからの書面を渡すことだ。
突然、彼女の前に屈強そうな、大柄の男が立ち塞がった。彼の背後に、見覚えのある男がこちらを見ている。——昨夜仕留め損ねた盗賊だとすぐに気がついた。何か小声で言い交わしながら、彼らはオラクルに近づいてくる。
「……勇敢なことだ。」
侮蔑に満ちたオラクルの呟きは、彼らの耳にも届いたらしい。大柄な男の表情は、すぐさま険しくなった。
「てめえ、随分と俺の弟分たちを可愛がって——」
男が言い終わるより先に、オラクルは思いっきり、彼の股間に蹴りを入れていた。突然の出来事に息を詰まらせるように喘ぎ、男は地面に這い蹲る。周囲の人々の視線は、一挙にオラクルと彼らに向けられた。何者なのか見定めようとする眼差し。
——不愉快だ。
その後のことは、オラクルの……オルティの八つ当たりに過ぎなかった。あっという間に彼らを「大人しく」させたオラクルに、人々は多少感心したらしい声を上げて、それから何事もなかったように散って行った。この程度のぶつかり合いは、おそらくこのキャンプでは茶飯事なのだろう。
ああ、何もかもが不快で苛立たしい。どうして、自分だったのだろう。オラクルは自問する。
世界を救う役に選ぶなら、もっと世界を信じて、愛している者の方が良かっただろうに。自分は——オルティ・クラヴィアドは、その役には相応しくないのだ。
◆
キャンプの中心部には、大きな広場があった。そこは綺麗に整備されており、露店が軒を連ねている。広場にはわずかながら花が植えられ、薄汚れていたが、道はタイルで装飾されていた。通りの奥には屋敷が見える。ラザロはそこにいるはずだ。
オラクルは真っ直ぐにそちらを目指す。館の入り口でアンセムに連絡を取る。ラザロは用心深い人のようで、面会に来たことをZeTAから証明させる必要があったのだ。
「オラクル、何かあったっスか? 元気ない感じするっスね」
アンセムは心配そうに声をかけてきた。彼女は妙に勘の鋭いところがある。
「いいえ、何でもありません」
「そうなんスか? なんか声に張りがないっていうか……。もしかして、風邪?流行ってるっスよね!?今日はしっかり休まないとダメっスよ! ラザロの旦那さんに言って、休ませてもらうように手配するっスから——」
「必要ありません」
「でも……」
アンセムは食い下がろうとする。朗らかで優しい、人のいい娘。アンセムのような者ばかりなら、もう少し世界を好きになれたかもしれない。世界を救う気概も持てようというものだ。
「……ありがとう、アンセム。……でも、私には本当に、必要ないのです。」
端末であるこの身体は、当然、風邪などひくことはない。しかし、せめてもの労いに、オラクルはそう言ってから通信を切った。
◆
ラザロのいる部屋は、屋敷の上階にあった。
オラクルが通された部屋は整然と整えられ、いかにも仕事のための部屋といった様子であった。ラザロは机に向かって、何か書類仕事をしていた。オラクルは後ろ手にドアを閉めると、ゆっくりと彼の方へと歩み寄っていく。左の眼を包帯で覆い、重い前髪が彼の表情を隠している。右眼は忙しなく、手元の書類の上を彷徨いていた。
ふと眼を上げた彼は一瞬、はっとしたようなそぶりを見せた。オラクル——オルティもまた、彼の相貌を食い入るように見つめていた。
——似ている。
ラザロの二藍の瞳が、戸惑うように、何かを悔やむように揺らめく。唇はかすかに、誰かの名前を辿るように開かれ、しかし彼は誰の名前も呼ばなかった。ややあって目を伏せ、再び目を開けた時には、ラザロの表情は事務的なものに戻っていた。オラクルも、何とはなく姿勢を正した。
「……ZeTAの使い、だな。」
ラザロが口を開いた。
「書類をよこすと聞いている」
オラクルは懐から、一通の手紙を取り出した。ラザロはそれを受け取ると、封を切り、目を通して微かに唇の端を歪めた。一瞬のことだったが、オラクルはそれをZeTAへの嘲笑だと感じた。
「ご苦労。……お前さん、此処へ来るのは初めてだな?」
ラザロははゆるやかに立ち上がると、返事を待たず、部屋の隅にある戸棚へと歩き出している。戸棚には大小様々な酒瓶が並べられていた。そこからボトルとショットグラスを手に取ると、ラザロはオラクルに、おそらく来客用であろう椅子に座るよう促した。
「一杯付き合ってくれるか?」
オラクルは躊躇ったが、結局は彼の言葉に従った。
美しい細工の施された机の上に、整然と並べられたグラス。ラザロがボトルを傾けると、琥珀色の液体がとくとくと注がれていく。そのグラスひとつひとつも、職人の手で作られたのだろう繊細なものであった。
オラクルは手渡されたグラスを手に取り、くっと傾けた。流れ込む、喉を焼くようなアルコールの味と、ぎゅっと詰められた穀物の熟れたこく、鼻腔に抜けていく微かな煙の香り。”オルティ”には懐かしい味わいだった。不思議なことにその味は、オルティが好んでいた品と良く似ていて、オラクルを感情に浸らせる。
ラザロは満足げにオラクルの様子を見ていたが、やがてゆっくりと語り始めた。
「偶々、俺の部下が見ていてなァ。盗品を捌こうが、俺の市場じゃあ咎める者はない。だが、それは少なからず恨みを買う。お前さんがやらなくても、いずれ始末された連中だ」
ラザロはそう言いながら、もう一杯酒を注いだ。オラクルは黙って話を聞く。
「お前さんのやったことに対して文句はない。むしろ、感謝してるくらいだ。これはその礼、ってこった。ま、気にせずに飲んでくれ」
オラクルは、目の前の男を静かに観察する。彼はオラクルを認めている。自分が認めたのだから、対等に扱う。……その感覚は、ひどく懐かしい心地がする。オラクルは目を伏せた。これは悪夢の神の悪戯か。運命、などという言葉は、使いたくなかった。自分と彼の間に結ばれたものを、そのように尊いものだと考えることは、”オルティ”にはひどく難しい。
「口に合わなかったか?」
「いえ……ただ。」
オラクルは首を振った。
「貴方が、二度と取り戻せない人に似ていたから。……本当に、それだけです。」
ラザロは目を細める。その言葉が彼の何を震わせたのか、彼は一瞬、泣きだしそうな子供のような顔をしたように、オラクルには見えた。
「……俺のことは、ラザロと呼んでもらって構わん。お前さん、名は?」
「オラクルです、ラザロ」
「いい名前だ」
「ありがとうございます」
二人はそれからしばらくの間、他愛のない会話を交わした。ラザロのはからいで、オラクルは館内に部屋を用意され、そこで休むことになった。やわらかな寝台に横たわり、オラクルは天井を見上げる。オラクルは眠る必要がない。——この端末の身体は、夢を見ないのだ。
ふと、ラザロの姿が脳裏に浮かぶ。話に聞く彼の姿とは、随分違っていた。ZeTAは彼をひどく警戒しており、オラクルが彼の元へ遣わされたのは、彼の様子を監視する意味もあったからだ。彼の築いた市場は、今やこの世界にとって重い意味を持つ。彼の機嫌を損ねることは、当然、ZeTAにとっても不利益である。
そして、彼にはいくつもの良くない噂があった。——このキャンプはZeTA禁制の品物も取り扱う。すなわち、麻薬の類や、ヒトやその骨肉ですら、彼らの扱う”品”である。ラザロが今の地位を築いたその発端は、ヒト、すなわち女の売り買いであったという話だ。彼自身もその贅を深く愉しんだという、真偽不明の話も添えられている。
だが、今日オラクルと出会った彼は、まるで牙の抜け落ちた老狼のような、落ち着いた様子であった。闘志や気概はまだその身体の底に残っていようが、もはや自ら牙を剥くことのないような印象。ひどく寂しげで、儚いとさえ思ったのだ。
それは、彼が誰かに似ているから、そう感じるだけなのだろうか。オラクルは起き上がり、部屋を出た。広い窓のある廊下から、前栽の広場を見下ろす。植えられたわずかな花は、彼の二藍の瞳に似た色の気がした。昨日よりも冴えた月は、淡く、かつ鋭く、金色の光を湛えていた。
「———、」
ふと、誰かの声が耳に届いた気がして、オラクルは勢い振り返る。申し訳なさそうに佇むラザロがそこにいた。
「……ラザロ?」
「あー……驚かせるつもりは……。」
「いえ……何か、私にご用ですか?」
「……んにゃ、何でも。……眠れないか?」
「ええ……そんなところです」
「俺も、だ」
ラザロは苦笑いすると、煙草を取り出して火をつけた。紫煙の行方を眺めながら、ラザロはオラクルに視線を向ける。
「なぁ、お前さん、いつまで居られる?」
「……もう一泊程度なら、ZeTAも許すでしょう」
それを聞いて、ラザロは嬉しそうに唇を綻ばせた。オラクルも、それを見ると何となく、気を許すつもりになったのだ。
「明日、少し時間をくれるか? その……無理にとは言わんが」
「構いません」
「そうか、良かった」
彼の笑顔は子供っぽい愛らしさを湛えていた。その笑顔におおよそ不釣り合いな煙草を咥え、ラザロの吐き出した煙は闇の中へと消えていく。
「折角遠いところを来てくれたんだ、俺の市場を見せたくてな?」
「それは……楽しみですね。」
「ああ、俺自ら案内しよう」
満足げに微笑むと、また一口、煙草を吸う。オラクルは、そんな彼をじっと見つめていた。
「どうした?」
「……ラザロ。貴方はどうして、私にそこまで良くしてくださるんですか」
「言ったろ? 感謝してるんだ。……それ以上に深い意味はねぇさ。」
「本当に?」
「嘘だと思うかい?」
オラクルは、彼の態度は嘘だと直感している。
ああ、思えば”彼”もそうだった。俺たちは、互いに嘘をかぶるのがうますぎた。寂しさを殺したまま、愛着を押し潰したまま、互いに何も口にしないままで、何よりも雄弁で饒舌だったのは互いの身体だけだったのだ。そのままで、”オルティ”は遂にここまで来てしまった。もう戻れず、取り返すこともできない。
——最後に見た彼は、ラザロと同じく、片眼を失っていた。それがオルティの心を決めた。失いたくないから、何よりも美しい思い出のまま、全てを手放したのだ。
「……貴方は…優しい人ですね、ラザロ。」
優しくて、寂しくて、愛おしい、俺だけの夜の月。
もう二度と帰れない、甘く美しい花の楽園。
オラクルは、滲んだ涙を溢さないよう、足早に与えられた部屋へと去った。その後姿を、ラザロは憂うように見つめていた。
◆
翌朝、オラクルはラザロに連れられて、彼の市場に足を運んだ。通りは人で溢れ返り、そこかしこから威勢の良い掛け声が聞こえてくる。
市場の売り物は様々だった。野菜、果物、肉、魚、衣類、装飾品、武具など、様々な商品が所狭しと並んでいた。その品揃えの豊富さは、ラザロ・キャンプならではのものだった。
市場の見回りは、おそらくラザロの仕事の一環なのだろう。ラザロは、道行く人々に気さくに声を掛けられていた。その様子から、彼が人望の厚い人物であることが分かる。人々が彼に敬意を表すたび、なぜだか、オラクルまでもが誇らしい気持ちになった。
市場をひと回りして、ふたりは屋敷の前へと戻っていた。広場では子どもたちがはしゃぎ回っている。オラクルとラザロは、広場に備えられた椅子(それも売り物のひとつであろう)にかけて、露店で分けてもらった飲み物を口にした。果物を絞ったものだろうそれは、水っぽくて薄い味ではあったが、歩き回った身体にはどことなく心地よい。……オラクルはそのような疲れを感じるようには出来ていないはずなのだが。
「良い市場だったろ? ……気に入ってくれたか?」
「ええ、とても気に入りました。……貴方の仕事ぶりも、貴方のことも。貴方はとても、立派に役を果たしている。」
オラクルは心からそう思っていた。”オルティ”として培った目は、こと商売に関しては鋭敏であった。その『彼』から見ても、ラザロの仕事は素晴らしいものだ。掛け値無しに、オラクルはラザロを評価していた。
しかしそれを皮肉と受け取ったのか、ラザロは自嘲するように微笑んだ。
「……そんな大層なもんじゃねぇよ。お前さんの思った通りだ。
……俺ァ、嘘を吐いた。」
風がふたりの間を通り抜ける。その風は、広場に植えられた花を、ふわりと散らして行った。
ラザロは、包帯に覆われた左眼を押さえる。悼むようなその仕草に、オラクルの胸はひどく痛んだ。……その先を聞いてはいけない気がしたのに、いつの間にか、言葉が口から漏れていた。
「……話してください、ラザロ。」
「つまらん話だ、忘れてくれ。」
堰を切った思いは、もう、止めることができなかった。
「……嫌だ、聞かせて欲しい。俺も、本当のことを話すから。だから……どうか、………許して。」
ラザロの瞳が動揺する。オラクルの後ろに、見えない誰かを見つめているかのように揺れる。
「貴方を身代わりにすることを、どうか許して欲しい。」
手を伸ばす。艶やかで繊細な神秘で出来た、白い手袋。オラクルの外装。熱を持たない、容れ物の体。触れたラザロの頬はひどく熱く、焼き溶かされてしまいそうなほど、人の温度を持っていた。
「本当に、愛していたんだ。俺は……誰よりも……貴方を愛していた。……でも、どうしても言えなかった。もっと早く言うべきだったのに、どうしても……!」
ラザロの頬に添えたオラクルの手に、ラザロの掌が重ねられる。
「言った方が、傷つけてしまうと思ったから……それなら最初から、何もないほうがいいと思ったから……。大切にしようとして……結局、何も言えないままになってしまった。だから……」
涙がこぼれ落ちて行く。
「だから、せめて、世界だけは救うから。貴方がもう何も失うことのないように、きっと、必ず、俺が守る。……はは……っ、本当は、そんなこと望んでないって、分かってるけどさ……!!」
「オリガ。」
不意に、ラザロは知らない名で、オラクルを呼んだ。
「……オリガ。もう泣くな。」
大きな掌で、オラクルの涙を拭い、眦に唇を寄せる。愛しげに、恋人にするように、オラクルの頬を撫ぜ、ラザロはオラクルを抱き寄せた。
ラザロの腕の中に包まれながら、オラクルはその好意を拒まなかった自身に驚きを隠せなかった。
——かつて同じように、その身を抱かれたことを思い出した。その熱をかなぐり捨ててきたことを思い出した。そうしてまで守りたかったものが、あったはずだ。忘れるわけがない。忘れるはずがない。
——ああ、鞍馬。俺はきっと、このまま全てを失ったとしても、この想いは、この熱だけは失わないだろう。
「……10年になる。お前さんが行っちまって……でも、まぁ、何とかやってる。分かってたさ、お前さんが意地張ってたことぐらい……だからもう、泣くな。俺ァ、ちゃあんと、分かってる。な?」
オラクルを解放して、ラザロはオラクルの髪を撫ぜながら笑った。そして、オラクルへと語りかけた。
「10年前だ。流行病で……女をひとり亡くした。オラクル、お前さんに良く似てる……意地っ張りで、気品があって……。あんまり呆気なく行っちまうから、俺ァ、何も出来ずに……。ZeTAと取引を始めたのも、彼奴を救うためだった。結局、連中は何の役にも立ちやせんかったが……まァ、役立たずは俺も同じだ。」
深く溜息を吐いて、ラザロは風が揺らす花に目をやる。
「あの花な、彼奴が植えたもんだ。俺の目に似てて好きだとか言ってな? 俺は手前ェの目なんざ、大っ嫌いだってのに……。私の好きな花みたいで綺麗なのに、意地悪言わないで、だとよ! …ふ、くく……っ。」
困ったように笑っている、その横顔を知っている。どれだけ綺麗だと褒めても、こんな気味の悪いもののどこが良い、と、彼も同じように笑っていたものだった。
「其奴のために世界を救う、なぁ……。オラクル……其奴は、そんなに俺に似てるのか?」
「ええ。とても。本当に、とても……。」
「ならきっと、其奴もお前に怒ったりしないだろう。俺のためなんかに頑張るな、なんて言うわきゃあねェ。よく頑張ったって、……頑張りすぎだ、ってちっとは言うかもしれんが……とにかく、そんなに俺が好きか、って笑う筈だ。俺が保証してやる」
ラザロはもう一度オラクルに向き直ると、二藍の瞳で真っ直ぐにオラクルを見つめた。
「悪かったなァ、オラクル。お前さんを彼奴の身代わりにしようとしたりして……。本当に。」
「いいえ、私こそ……ごめんなさい。でも……おかげで、私の覚悟は決まりました。もう、迷いません。」
「そうかい。なら、良かった。」
暖かな沈黙が、風に流れて行く。
オラクルの心は決まっていた。胸には暖かい熱が灯っている。世界のためだなんて、思わなくたっていい。自分の理由が彼だけだって構わない。彼と、彼の愛してくれたぶんと、自分の手が及ぶ範囲だけで。それだけでも構わない。それがオルティ・クラヴィアドの守るべきものなのだから。
——その役に相応しいのは、自分だけなのだから。
◆
翌日、オラクルがキャンプを去る時、ラザロは市場の入り口まで見送りに来ていた。
「もう少し待てるなら、用意した荷ごと運んでやるんだが」
ラザロは残念そうに言う。オラクルは首を振った。
市場の入口には、荷物を積んだ馬車が何台か停められていた。その周りでは、商人達が忙しなく働いている。ZeTAとの取引品だろう。
「いいえ、本部へは戻りません。このまま、次の仕事に向かいますから」
オラクルの表情は晴れやかだった。ラザロは、オラクルの言葉を聞くと、寂しそうに苦笑した。
小さな電子音が耳元で聞こえる。アンセムからの通信だろう。
オラクルは、ラザロに別れを告げると、その場を離れた。
「おはよっス、オラクル!定時連絡の時間っスよ!元気してるッスか?」
「おはようございます、アンセム。こちらは特に問題ありません」
「そっか、それなら良かった。……なんか、元気そうスね。ゆっくり休めたみたいで、アタシは安心ス!それで、次の目的地なんスけど、デルファイ・キャンプってところで……」
アンセムの言葉を聞きながらふと振り返ると、ラザロは彼女に気づいて手を振った。オラクルも手を振り返す。
やがてラザロの姿が見えなくなると、オラクルは真っ直ぐに前を向いて、歩き始めた。